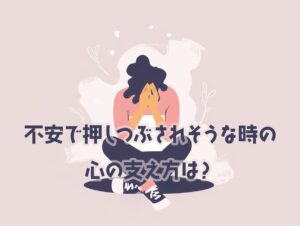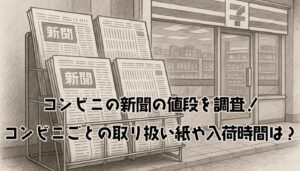スープジャーを使ったお弁当は便利ですが、腐るリスクや入れてはいけない食材があることをご存知でしょうか?
本記事では、スープジャーに入れたものが腐る原因とその防止策について詳しく解説します。
スープジャーに入れたものって腐るの?
結論から言うと、腐ることがあります。
具体的には、下記のような原因が重なると、腐るリスクが高まります。
スープジャーに入れたものが腐る原因
温度管理が不適切
スープジャーの中身が腐る最大の原因は、適切な温度管理ができていないことです。
食中毒菌は35℃前後の温度で最も活発に増殖します。
スープジャーの保温力が十分でないと、中身の温度が35℃付近まで下がってしまい、細菌が繁殖しやすい環境になってしまいます。
また、スープジャーには熱々の汁物を入れましょう。
85℃以上の高温なら、ほとんどの食中毒菌は死滅します。
しかし、十分に加熱していない汁物を入れると、食中毒菌が生き残ったまま保温されてしまい、増殖のリスクが高まります。
保存時間が長すぎる
スープジャーに汁物を入れて長時間保存することも、腐敗のリスクを高めます。
一般的に、スープジャーのメーカーは6時間以内に中身を食べきることを推奨しています。
6時間を超えると、たとえ初期温度が高くても、徐々に温度が下がり、食中毒菌が増殖しやすい環境になるためです。
特に、前日に作った汁物を翌日のランチに持っていく場合は要注意です。
常温で一晩放置すると、食中毒菌が増えている可能性が高くなります。
前日に作った汁物は、必ず冷蔵庫で保存し、当日の朝に再加熱してからスープジャーに入れるようにしましょう。
衛生管理が不十分
スープジャーの衛生管理が不十分なことも、腐敗の原因になります。
汁物を作る際に、手指や調理器具を介して食中毒菌が混入するリスクがあります。
また、スープジャー自体が汚れていたり、隅々まで洗えていなかったりすると、細菌が繁殖しやすい環境になってしまいます。
食材は新鮮なものを使い、調理前にはしっかりと手を洗うこと、まな板や包丁などの調理器具は清潔に保つことが大切です。
また、スープジャーは使用後に丁寧に洗浄し、乾燥させてから保管するようにしましょう。
スープジャーの温度管理方法
予熱する
スープジャーの保温力を最大限に発揮させるためには、予熱がベストです。
予熱することで、スープジャー内部の空気を温め、保温効果を高めることができます。
予熱の方法は簡単です。
まず、熱湯を沸かします。
そして、スープジャーの内側の線から1cm下までその熱湯を注ぎ、蓋をして1~5分ほど置いておきます。
汁物を入れる直前に、この熱湯を捨てれば準備完了です。
予熱をしっかり行うことで、汁物の初期温度を高く保つことができ、食中毒菌の増殖を抑えることができます。
また、スープジャー内部も殺菌されるので、衛生面でもメリットがあります。
予熱を行わないと、スープジャーに入れた瞬間にスープの温度が急激に下がり、菌の繁殖しやすい温度帯に達してしまうリスクが高まります。
スープジャーを使う際は、なるべく予熱を行うようにしましょう。
この一手間が、美味しく安全にスープジャーを使うためのポイントです。
沸騰させてから入れる
スープジャーにスープを入れる際は、必ず沸騰させてから入れることが重要です。
85℃以上の高温になると、ほとんどの食中毒菌は死滅します。
沸騰させることで、スープの温度を高く保ち、菌の繁殖を防ぐことができます。
スープジャーに入れる直前に沸騰させることで、予熱効果も期待できます。
スープジャーは、内部が温かいほど保温効果が高まるため、スープ自体の温度が高いとより長持ちします。
朝に作ったスープを昼まで安全に保つためには、この点を意識してみてください。
保温バッグを使う
スープジャーの保温力をさらに高めるために、保温バッグの活用がおすすめです。
保温バッグに入れることで、外気温の影響を受けにくくなり、味噌汁の温度低下を防ぐことができます。
特に、冬場の寒い時期や、エアコンの効いた室内では、スープジャーの温度が下がりやすいため、保温バッグが役立ちます。
また、バッグに入れることでスープジャー本体を傷から守り、汁漏れした時に持ち物が汚れることからも守ります。
市販の保温バッグは手軽に入手でき、デザインも豊富です。
スープジャーと一緒に活用することで、いつでも温かいスープを楽しむことができますよ。
衛生管理のポイント
調理器具を清潔に
スープジャーを使用する際には、調理器具の清潔さを保つことが非常に重要です。
包丁やまな板、鍋など、スープの調理に使用する器具は、使用前後にしっかりと洗浄し、除菌しましょう。
まな板は生肉や魚を切った後に特に細菌が付着しやすいため、熱湯をかけるなどして徹底的に消毒することが大切です。
調理器具が清潔でないと、スープに細菌が混入し、腐敗の原因となります。
スープジャーに入れる前に調理器具の清潔さを確認し、衛生的に保つことが安全な食事を楽しむための基本です。
これにより、スープジャーの中身が腐るリスクを大幅に減らすことができます。
新鮮な食材を使い、傷みやすい食材は避ける
スープジャーに入れるスープを作る際には、新鮮な食材を使用することが重要です。
新鮮な食材は、細菌の繁殖が少なく、安全に調理することができます。
食材に異臭がしたり、表面に変色やカビが生えていたりする場合は、使用を控えましょう。
傷みやすい食材の例
- 味噌汁の具材では
豆腐、じゃがいも、あさり、なめこなどの具材は傷みやすく、菌が繁殖しやすい傾向にあります。
元々水分が多い、または水分を吸いやすいため、温度が下がりやすいのです。
こういった具材は、避けるか、必ず当日の朝にしっかり火を通して早めに食べてしまいましょう。
特に、じゃがいもの芽や緑色の部分には、ソラニンという有毒成分が含まれているので、しっかりと取り除きましょう。
ソラニンが加熱不十分な状態で摂取されると、健康被害を引き起こすことがあります。
スープジャーにじゃがいもを入れる際は、前日に茹でておき、翌朝にスープに加える方法が安全です。
じゃがいもは火が通りにくいので、あらかじめ茹でておくことでスープ全体が均一に加熱され、安全に食べることができます。- 生卵
生卵は非常に傷みやすく、適切な加熱を行わないとサルモネラ菌などの食中毒の原因になる可能性があります。
卵を使った中華風スープを作る際には、スープ全体が十分に沸騰してから溶き卵を加え、完全に火が通るまで加熱します。
その後、スープジャーに移します。
ゆで卵のように、しっかりと加熱した卵であれば問題ありません。
この場合は、沸騰したお湯でゆで卵を作り、殻をむいてからスープジャーに入れましょう。- 乳製品
乳製品は腐敗しやすい食品のため、スープジャーに入れるのは注意が必要です。
牛乳やクリームなどの乳製品を使ったシチューやスープは、スープジャーの中で温度が下がると腐りやすくなってしまいます。
乳製品を使った料理をスープジャーに入れる場合は、必ず一度加熱調理したものを入れましょう。
生の状態や加熱が不十分だと、腐るリスクが高いです。
また、スープジャーに入れてから長時間放置せず、なるべく早めに(6時間以内に)食べきるのがおすすめです。
乳製品を使った料理は腐敗すると食中毒の原因になるため、少しでも怪しいと感じたら食べずに捨てるのが賢明です。
一度に食べきる
スープジャーに入れた料理は、一度に食べきるのが理想的です。
蓋を開けた瞬間から、スープの温度は下がり始めます。
何度も蓋を開け閉めすることで、温度変化が大きくなり、細菌が繁殖しやすい環境になってしまうのです。
また、一度口をつけたお箸やスプーンを再度使うのは、衛生的によくありません。
残さず、一気に食べきることを心がけましょう。
スープジャーのお手入れ
スープジャーを清潔に保つことは、基本中の基本です。
使用後はすぐに洗浄し、食品の残りや汚れが付着したまま放置しないことが重要です。
毎日の使い終わりには、必ず中性洗剤でしっかりと洗浄し、乾燥させてから保管するようにしましょう。
特に、パッキンの部分は、細菌が繁殖しやすい場所です。
パッキンを取り外して、隅々まで洗浄することが大切です。
また、スープジャー本体も、内側だけでなく、外側も丁寧に洗うことを心がけましょう。
定期的に、煮沸消毒を行うのもおすすめです。
スープジャーを分解し、各パーツを鍋に入れて、10分ほど煮沸することで、目に見えない細菌も確実に除去され、安心して使用することができます。
煮沸後は、十分に乾燥させてから組み立てましょう。
清潔なスープジャーを使うことで、安心して汁物料理を楽しむことができます。
面倒に感じるかもしれませんが、衛生管理のために、こまめな洗浄を習慣づけることが大切ですね。
食洗機は使えるの?
食洗機対応のスープジャーもあります。
食洗機は高温洗浄が可能なので、こういったタイプだと毎日清潔に使うことができますね。
電子レンジは使えるの?
電子レンジ対応のスープジャーもあります。
ただし、保温力の高いステンレスタイプはレンジ不可で、プラスチックなど少し保温力が落ちるものがレンジに対応しているという印象です。
持って行く先に電子レンジがあるかどうかで、どういったスープジャーにするか決めるのもよいでしょう。
スープジャーに向いている料理・向いていない料理
ここでは、メジャーな料理のスープジャーとの相性と注意点をまとめてみました。
カレー
カレーはスープジャーの保温力を活かせる料理です。
温かいまま保温すると、味がよくなじみ、カレーの風味が落ちにくいです。
比較的保存が利く料理ですが、スープジャーに入れる前に必ず沸騰させ、長い時間放置しないように気をつけましょう。
シチュー
シチューはスープジャーとの相性が良い料理です。
ただしクリームシチューの場合は、乳製品が食中毒のリスクを高めるため、早めに食べるようにしましょう。
スープジャーに入れる前にしっかりと加熱し、熱いうちに入れます。
麺料理
麺は、袋の表示より少し短めに茹でて、水でよく洗って水気をしっかり切り、小さじ1程度のごま油をからめておくとくっつきにくくなります。
うどん・そば・ラーメンなどの麺料理は、汁のみをスープジャーに、麺は別容器に分けるのがおすすめです。
長時間麺をスープに浸しておくと、麺が汁を吸って柔らかくなりすぎ、風味が落ちてしまいます。
温かいものでも冷たいものでも持ち運びが可能です。
パスタはなるべくオイルベースのものを選びましょう。
クリームソースなど乳製品を使ったものは腐るリスクが高まります。
そうめんは水分が多いので、他の麺料理より少し気をつける必要があります。
特に温かい状態で持ち運ぶとリスクが高まるので、持ち運ぶなら冷たいそうめんで。
味噌汁
味噌汁はスープジャーと相性が良く、温かいまま持ち運べるので非常におすすめです。
ただし、豆腐、じゃがいも、あさり、なめこなどの食材は傷みやすいため注意が必要。
わかめやねぎがおすすめです。
前日に作った味噌汁は、必ず冷蔵保存し、当日の朝から沸騰させましょう。
常温で保存していた場合は食中毒菌が増殖している可能性があります。
おでん
おでんはスープジャーにとてもよく合う料理です。
保温することで味がしっかりしみこみます。
米、もち麦、オートミールなどを含むもの
雑炊やリゾットなど米を含む料理の場合、米が汁を吸ってしまうので汁を多めに入れた方が良いです。
あるいは、麺料理と同じように米と汁を分けて持ち、食べる直前に混ぜるなど。
もち麦も汁を吸いやすく、汁につけたままだとかなり膨張します。
また、長時間保温で風味が変わることがあるので注意。
ただし血糖値があがりにくく、ダイエットにもよい食材です。
オートミールはスープジャー向きの食材です。
米ほど汁を吸うこともなく、ごはんにも甘い料理にも使えます。
水溶性・不溶性の食物繊維が豊富で腸活効果もあります。
ダイエットにおすすめ。
鍋(の残り)
具材によって腐りやすいものが含まれるため注意が必要です。
特に肉や魚介類が入っている場合は注意。
前日の鍋の残りは、必ず冷蔵保存し、当日沸騰させてからスープジャーに入れます。
また、スープジャーに入れる予定があるなら、鍋を食べる際は口をつけた箸でつつかないようにあらかじめ注意。
スープジャーを使ったレシピ例
持ち運びしやすいスープのレシピ例をいくつかご紹介します。
分量は、お使いのスープジャーの容量に合わせて調節してください。
野菜たっぷりミネストローネ
玉ねぎ、にんじん、セロリ、ジャガイモ、ベーコンを炒める。
水、コンソメ(水400mlにキューブ1個(小さじ2杯)程度)、トマト缶を加えて煮込む。
最後にキャベツとマカロニを加え、塩、こしょうで味を調える。
熱々のスープをスープジャーに注ぎ、蓋をする。
中華風コーンスープ
鶏がらスープを沸騰させ、クリームコーン缶、コーン缶を加える。
溶き卵を回し入れ、塩、こしょう、ごま油で味を調える。
熱々のスープをスープジャーに注ぎ、蓋をする。
簡単!オートミール茶漬け
まとめ
スープジャーを使用する際は、適切な温度管理と衛生管理が不可欠です。
味噌汁などの汁物が腐敗するのを防ぐためには、以下の点に注意しましょう。
- スープジャーを熱湯で予熱する。
- 当日の朝に作り、沸騰させてからスープジャーに入れる。
- スープジャーの内側の線から1cm下までスープを入れる。
- なるべく早く(6時間以内に)食べる。
- 一度に食べきる。残さない。
また、豆腐やなめこ、じゃがいもなどの食材は、新鮮なものを使えば問題ありません。
ただし、前日に作った料理は、冷蔵庫で保存し、当日に再加熱してからスープジャーに入れましょう。
生卵については、食中毒のリスクがあるので、スープジャーに入れるのは避けた方が無難です。
加熱調理した卵であれば問題ありませんが、衛生管理には十分気をつけましょう。