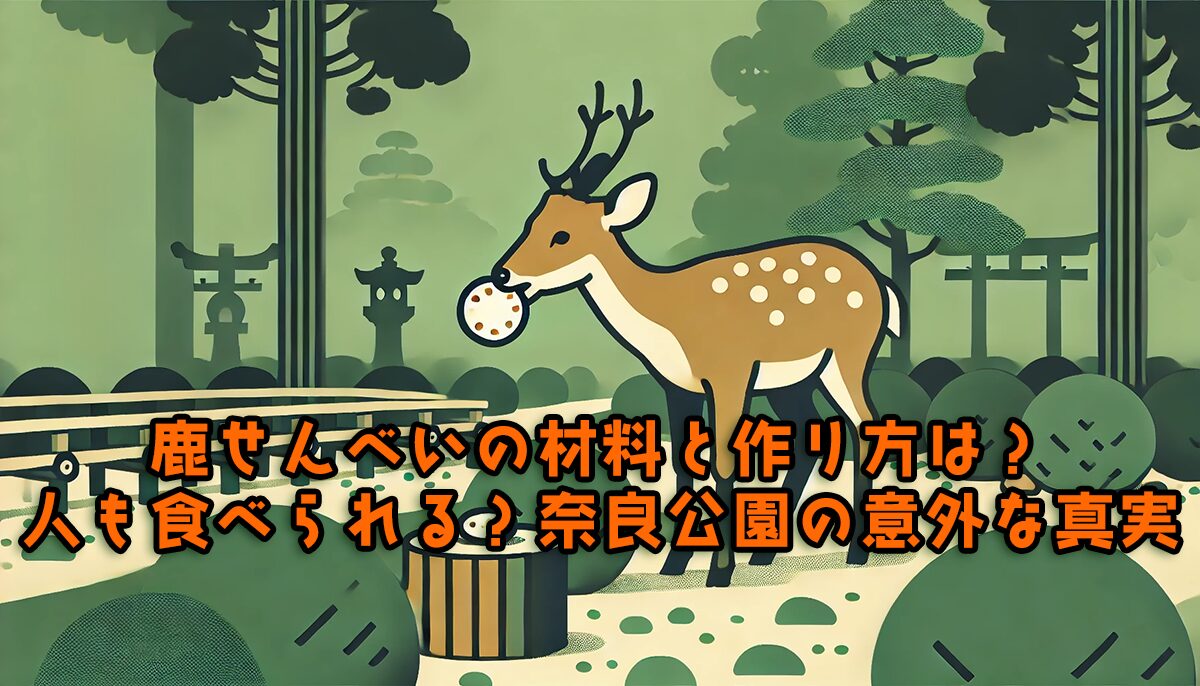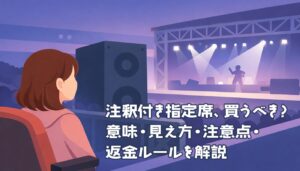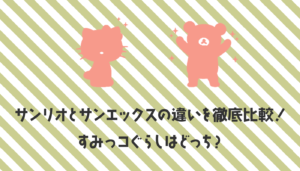鹿せんべいの基本情報
鹿せんべいとは

I, Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
鹿せんべいは、奈良公園で観光客に親しまれている鹿のためのおやつです。
主に鹿の健康を考えて作られており、シンプルで自然な成分のみが使用されています。
見た目は一般的なおせんべいと似ていますが、その目的と製造過程は大きく異なります。
鹿の栄養と健康を第一に考えて作られた特別な食べ物なのです。
鹿せんべいは主食ではない!?
鹿の食べ物=鹿せんべいのイメージが強いですが、鹿は鹿せんべいしか食べていないわけではなく、主食は芝やどんぐりなどの草食動物です。

Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
愛護会の獣医師によると、鹿せんべいは草よりも高カロリーではありますが、1枚3~4gしかないため、たとえ何十枚食べたとしてもおやつの範疇なんだそうです。
歴史
鹿せんべいの歴史は意外と古く、江戸時代にはすでにそれらしきものが存在していたようです。

せんべいのような平面状のえさを鹿に与えている姿が見える。
日本語: 竹原春朝斎English: Shunchosai Takehara, Public domain, via Wikimedia Commons
奈良公園における役割
鹿せんべいは、奈良公園における鹿と観光客の交流の重要な架け橋となっています。
観光客は鹿せんべいを購入し、鹿に与えることで、直接的に鹿とふれあうことができます。
また、鹿せんべいの売上の一部は鹿の保護活動に充てられており、地域の生態系保護にも大きく貢献しています。
単なるおやつ以上の、重要な社会的意義を持つ食べ物なのです。
鹿せんべいは、観光客に鹿との触れ合いの機会を提供するだけでなく、奈良の伝統文化と自然保護の精神を体現する、まさに奈良公園を象徴する存在と言えるでしょう。
観光客は鹿せんべいを通じて、鹿との特別な交流を楽しむことができるのです。
鹿せんべいの材料と作り方
主な原材料

https://www.flickr.com/people/jerrylai0208/, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
鹿せんべいの原材料は、驚くほどシンプルです。
主成分は「米ぬか」と「小麦粉」の2つのみです。
この理由は、鹿の健康と栄養を徹底的に考慮しているからです。
米ぬかは、米の精米過程で生じる外皮の部分で、栄養価が非常に高い食材です。
タンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれており、鹿の健康維持に最適な成分となっています。
小麦粉は、生地を形成し、せんべいに適度な硬さと食感を与える役割を果たします。
これらの材料は、鹿にとって消化しやすく、栄養価が高いため慎重に選ばれています。
証紙も食べられる素材でできている

鹿せんべいに巻かれている証紙も、食べられる素材で作られている徹底ぶりです。
素材は100%パルプ、大豆インク、食べられるノリ。
間違って鹿が食べてしまっても、健康を害することのないように配慮されているのです。
この証紙がかけられている鹿せんべいが公式のもので、売り上げは怪我をした鹿の保護活動や、鹿の出産補助の費用に充てられています。
鹿せんべいの作り方
意外なところで、鹿せんべいの作り方が公開されていました。
アニメ『しかのこのこのここしたんたん』のEDが、鹿せんべい工場での製造過程になっています。
自作するなら?
奈良から遠く離れた地でも、鹿せんべいに触れてみたい…という場合は、下記レシピを参考にしてみて下さい。
人間用のおせんべいの作り方と変わりありません。
<材料>
- 米ぬか(油の浮いていない新しいもの)
- 小麦粉
- 水
<作り方>
- 米ぬかと小麦粉をだいたい6:4の比率で混ぜ合わせる
- 水を少しずつ加え、お好み焼きの生地程度にトロリとするまで練る
- 予熱したホットプレートやフライパンに、厚さ3~4mm程度に丸く広げ、両面5分ほど焼く
- 10枚ずつ証紙を巻いてできあがり
なお、奈良公園で売られている鹿せんべいはきちんと検品されています。
このレシピで作った鹿せんべいは実際に鹿にあげるのではなく、雰囲気を楽しむ用途でお使い下さい。
人間用おせんべいと鹿せんべいはどう違う?
鹿せんべいに添加物を使用しない理由
鹿せんべいには、余計な添加物、保存料、甘味料が一切加えられていません。
これには明確な理由があります。
鹿の消化器系は、人間とは大きく異なります。
余分な添加物や人工的な成分は、鹿の健康を害する可能性があるため、徹底的に排除されています。
例えば、人間用のおせんべいに使用される砂糖や塩、人工的な調味料は、鹿がお腹を壊したり、有害となる可能性があるのです。
人間用の食べ物はあげないようにしましょう。
人間用おせんべいとの違い

Midori, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
人間用のおせんべいと鹿せんべいの最大の違いは、添加される成分にあります。
通常、人間用のおせんべいには砂糖や塩、味を強化するための各種フレーバーが添加されています。
醤油、サラダ、えび、チーズなど、多種多様な味付けのおせんべいを見つけることができます。
鹿せんべいは、鹿の食べ物として特化しているため、鹿の健康を損なう可能性のある成分は徹底的に避けられています。
このため、味付けがされていないのです。
人間が鹿せんべいを食べるとどうなる!?
一言で言うと、オススメはしません。
原材料的には、人が食べても問題はありません。
だって米ぬかと小麦粉ですから。
ただし、味付けはされていないので非常に薄味です。
過去に鹿せんべいは新聞紙でできているという噂が立ったこともありますが、これはおそらく人が鹿せんべいを食べたときの味気なさと、せんべい自体の物理的な薄さを揶揄したものではないでしょうか。
また、本来は人が食べるものではないため、消費期限が設けられていません。
最近はインバウンドも多く、鹿せんべいを買い求める人も多いため、あまりないことだとは思いますが、たまたま食べたものがものすごく古い鹿せんべいだった…ということが絶対ないとも言い切れません。
鹿が食べてはいけないものとは

tetchang, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
鹿が食べてはいけない食べ物
奈良公園の鹿に与えてはいけない食べ物には、いくつか重要な注意点があります。
観光客が誤って与えてしまう危険な食べ物もあるので、しっかりと理解しておく必要があります。
特に危険な食べ物には以下のようなものがあります。
- パンやお菓子
砂糖、油、添加物などが含まれているため、鹿の消化器官に負担をかけるおそれがあります。
また、匂いを覚えるとビニールゴミを漁って誤飲してしまう可能性があります。
ビニールは消化できないため、最悪命に関わる危険があります。- 野菜など農作物
味を覚えると、近隣の農作物を食い荒らすようになるおそれがあります。
農作物被害を引き起こす鹿は、鹿苑(鹿の保護施設)に収容されてしまいます。
軽い気持ちで与えたものが、深刻な健康被害を引き起こしたり、鹿を閉じ込めることになります。
くれぐれも人間用の食べ物は与えないようにしましょう。
鹿の消化器系の特徴
鹿の消化器系は、草食動物特有の非常に繊細な仕組みになっています。
鹿の胃は4つの区画に分かれており、植物性の食物を効率的に消化するように設計されています。
人間の食べ物や加工食品は、この複雑な消化システムを混乱させる可能性が高いのです。
特に、炭水化物や糖分の多い食べ物は、鹿の腸内細菌のバランスを崩し、深刻な消化器系の問題を引き起こす可能性があります。
危険な食べ物と健康被害
鹿に不適切な食べ物を与えると、以下のような深刻な健康被害が発生する可能性があります。
- 消化不良
- 腸閉塞
- 腸内細菌叢の破壊
- 栄養吸収の阻害
- 重度の下痢
- 潰瘍
- 最悪の場合、死亡リスク
特に注意が必要なのは、人間の食べ物や加工食品です。
これらは鹿の自然な食生活と全く異なるため、消化器系に大きな負担をかけます。
奈良公園では、鹿せんべい以外の食べ物を与えないよう、ルールを設けています。
鹿の健康と安全を守るためには、指定された鹿せんべいのみを与えてください。
鹿の健康を第一に考え、適切な方法で鹿とふれあいましょう。
鹿せんべいは、鹿の栄養と健康を考えて作られた、唯一安全な餌なのです。
鹿せんべいのあげ方
鹿せんべいの購入場所
鹿せんべいは、奈良公園内の移動型販売所、土産物屋、茶店などで売られています。

Hirojin taja, Public domain, via Wikimedia Commons
売店の数は多いので、公園内を少し歩けばすぐに見つかるはずです。
現在(2024年)の価格は10枚1セットで200円。
ちなみに、「奈良の鹿はなぜかせんべい販売所のせんべいを奪わない」という都市伝説がありますが、デマだそうです。
実際は、販売員の方々が地道に「口で言って聞かせている」そうです…。

安全な鹿との触れ合い方
鹿との触れ合いには、安全に関する重要なガイドラインがあります。
まず、鹿に背後から近づいたり、急な動きをしたりしないことが大切です。
鹿は警戒心が強い動物なので、ゆっくりと落ち着いて接近しましょう。
せんべいを与える際は、鹿の目の高さまで手を下げ、優しく差し出します。
鹿が興奮したり、威嚇したりする兆候が見られたら、すぐにその場を離れることが重要です。
子供と一緒に鹿と触れ合う場合は、特に注意が必要です。
子供の動きは予測できないため、常に大人が付き添い、安全を確保する必要があります。
鹿せんべいがなくなったら
両手を見せ、「もうないよ」と鹿にアピールしましょう。
隠していても匂いでばれるようなので、潔くさっさとあげてしまいましょう。
「まだ持っているな」と鹿に思われたら、集団でついてこられることがあります。
鹿の気が荒くなるとき
鹿は9月~11月が発情期とされ、この頃が一年で一番気が荒くなります。
ピークは10月下旬と言われています。
この時期は、鹿に無理矢理触れたり、必要以上に近づいたり、不用意にからかったりすることは危険です。
特にオスの鹿には注意しましょう。
角があるのがオスの鹿です。
奈良の鹿といえば「おじぎ」だけど…
「おじぎ」をすることで有名な奈良公園の鹿。
しかし、このお辞儀は「感謝」「礼儀正しさ」「サービス」などで行っているのではありません。
「こうすると鹿せんべいをもらえる」というような学習、つまり生存本能によるものです。
おじぎをする鹿はかわいいですが、おじぎ見たさに鹿せんべいを焦らしすぎると怒らせてしまうことがあるかもしれません。
鹿せんべいをあげる際は、撮影もほどほどに。
鹿せんべいはただの鹿のおやつじゃなかった!
持続可能な鹿保護への貢献
鹿せんべいは、単なる観光土産以上の重要な役割を果たしています。
奈良公園には約1,200頭の鹿が生息しており、その保護と維持は地域にとって重要な課題となっています。
鹿せんべいの売上の一部は、直接鹿の保護活動に充てられます。
これにより、観光客は鹿せんべいを購入するだけで、鹿の保護に貢献することができるのです。
具体的には、餌の確保、健康管理、生態系の維持など、鹿の生活を支える様々な活動に資金が使われています。
観光と保護のバランス
奈良公園における鹿せんべいは、観光と自然保護のバランスを取る上で重要な役割を果たしています。
年間約900万人が訪れる奈良公園において、鹿せんべいは観光客と鹿をつなぐ架け橋となっています。
観光客は鹿せんべいを通じて、鹿と安全に触れ合うことができます。
同時に、鹿の生態や保護の重要性について学ぶ機会も得られます。
これにより、単なる観光地としてだけでなく、自然教育の場としての価値も高まっているのです。
鹿愛護会は、観光客の増加が鹿に与える影響を常に注意深くモニタリングしています。
鹿せんべいの販売方法や使用方法を通じて、鹿の健康と観光客の体験のバランスを保つ努力を続けているのです。